原油高で一番打撃を受ける国は?
国際原油価格が年内に100ドルまで上昇する可能性が提起されている中、原油高による被害がアジアの新興国に集中されると予想されている。ウォール・ストリート・ジャーナルは27日、アジア諸国の中で経常収支が良好なフィリピンと中国も原油高を警戒していると報じた。
フィリピンの7月国内総生産(GDP)比率の経常収支赤字規模は0.6%で、それぞれ1.9%と2.3%を記録したインドとインドネシアより低い。しかしフィリピンの8月の物価上昇率は過去10年間で最も高い6.4%を記録し、景気過熱が鮮明となっている。さらに原油価格の上昇も経済の負担になっている。高い水準を見せるインフレ率に原油高の負担が加わって経済成長率が下落すると、自国通貨ペソの価値が打撃を受けると予想されている。
中国も米国との貿易摩擦などにより、物価が急速に上昇している。最近は輸入量が増え、経常収支の黒字規模は3年前の700億ドルから58億ドル(今年2四半期)に減った。米国の追加関税と原油高まで重なったため、黒字幅はさらに減少するとみられる。専門家らはこういう経済環境から「人民元安は避けられない」と分析している。人民元安は新興国の輸出競争力の低下につながる。
ウォール・ストリート・ジャーナルは「中国経済の成長鈍化に耐えてきたアジア諸国が、原油高と人民元安、米国の金利引き上げといった悪材料に直面している」と報じた。
■原油100ドル時代の再来
ロンドン市場で北海ブレント原油先物が今週24日、1バレル80ドルを突破した。80ドル台を超えたのは2015年以来初となる。11月からは米国のイラン制裁が再開され、原油供給量が急減すると予想される。一部の専門家は年内に1バレル100ドルの可能性を提起している。
イランは昨年夏の時点から世界の一日石油消費量の3%にあたる270万バレルを毎日輸出してきた。対イラン制裁が本格的に発動されれば、供給量は一日約50~200万バレル減少するとみられる。
ブレント原油は27日、前日より0.65%上昇した81.87ドル台で取引されている。ニューヨーク市場のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物も小幅上昇し、72.32ドルを記録した。
Copyright © The financial news japan. All rights reserved.
ファイナンシャルニュースジャパン

.jpg)





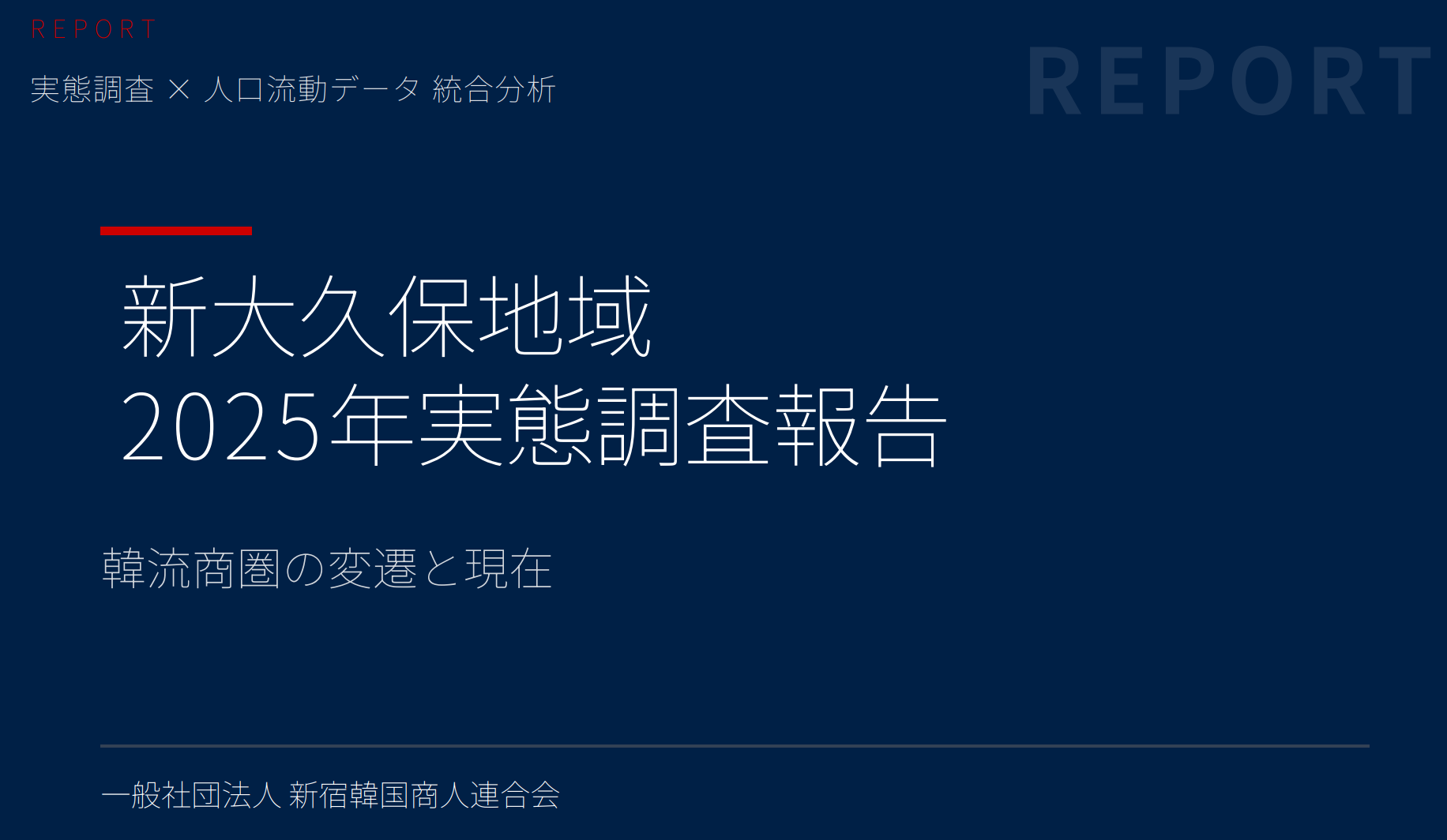





Leave a Reply