アジア新興国の来年成長率が18年ぶり低水準に
アジア新興国の来年経済成長率が貿易戦争と景気鈍化、米国の金利引き上げ、ドル高などの悪材料により18年ぶりに低い水準を記録するという見通しが出た。英紙フィナンシャル・タイムズによると、専門家らは、実際に成長率が墜落した場合、下落基調は少なくとも2022年まで持続すると予想している。
調査会社フォーカス・エコノミックスは世界90カ所の銀行と資産運用会社、コンサルティング会社、格付け会社を対象にアンケート調査を行い、来年度のアジア新興国(19ヵ国)の平均GDP(国内総生産)成長率が5.8%にとどまると予測した。これは2001年に米国で「ドットコムバブル」が崩壊した時の成長率(5%)以来、約18年ぶりの低水準。
分析結果によると、このような下落は少なくとも2022年まで続く見通しで、GDP成長率は5.3%まで低下すると推定される。国際通貨基金(IMF)は4月の報告書で、アジア新興国30ヵ国のGDP成長率が今年から2020年まで6.5%に停滞し、2022年に6.3%になると予測した。
フォーカス・エコノミックスのリカルト・トルネ氏は「成長鈍化は数年間避けられない」とし、「アジア新興国が今年の3・4四半期から、国際的な成長率の鈍化と貿易紛争による被害を受け始めた」と説明した。また「中国と台湾では今年7〜8月の製造業購買担当者景気指数(PMI)が下落傾向を見せており、韓国はすでに萎縮の領域に入っている」と述べた。
今回の調査によると、アジア新興国を率いる中国のGDP成長率が来年に6.3%を記録し、今年より0.3%下落するとみられる。2022年までは毎年0.3%前後の割合で減少していくと予想される。この成長率は、2007年の14.7%の半分にも満たない水準だ。
成長鈍化の原因は様々だが、特に米中の貿易摩擦が根本的な原因ではないという分析が注目を集めている。英国調査会社キャピタル・エコノミクスのゲリス氏は「中国が今年7〜8月に米国に輸出した物量は今年2四半期の平均よりも増えており、中国に中間財を輸出する韓国と台湾の対中国輸出規模も維持されている」と強調。同氏は「中国の成長鈍化は、米国との全面的な貿易戦争がなかったとしても発生した」とし、「内需中心の経済に転換しようとする中国政府の経済計画自体が成長鈍化を招いた」と分析した。
しかし大体の海外専門家らは、アジア新興国の人口変化と遅い改革速度、社会基盤施設の脆弱性などが成長の妨げとなっていると分析した。
米国の金利引き上げも悪材料だ。新興国の中央銀行が資金流出を防ぐため、米金利に沿って自国の政策金利を引き上げると、低迷した景気にさらなる悪影響になる可能性が高い。
Copyright © The financial news japan. All rights reserved.
ファイナンシャルニュースジャパン

.jpg)





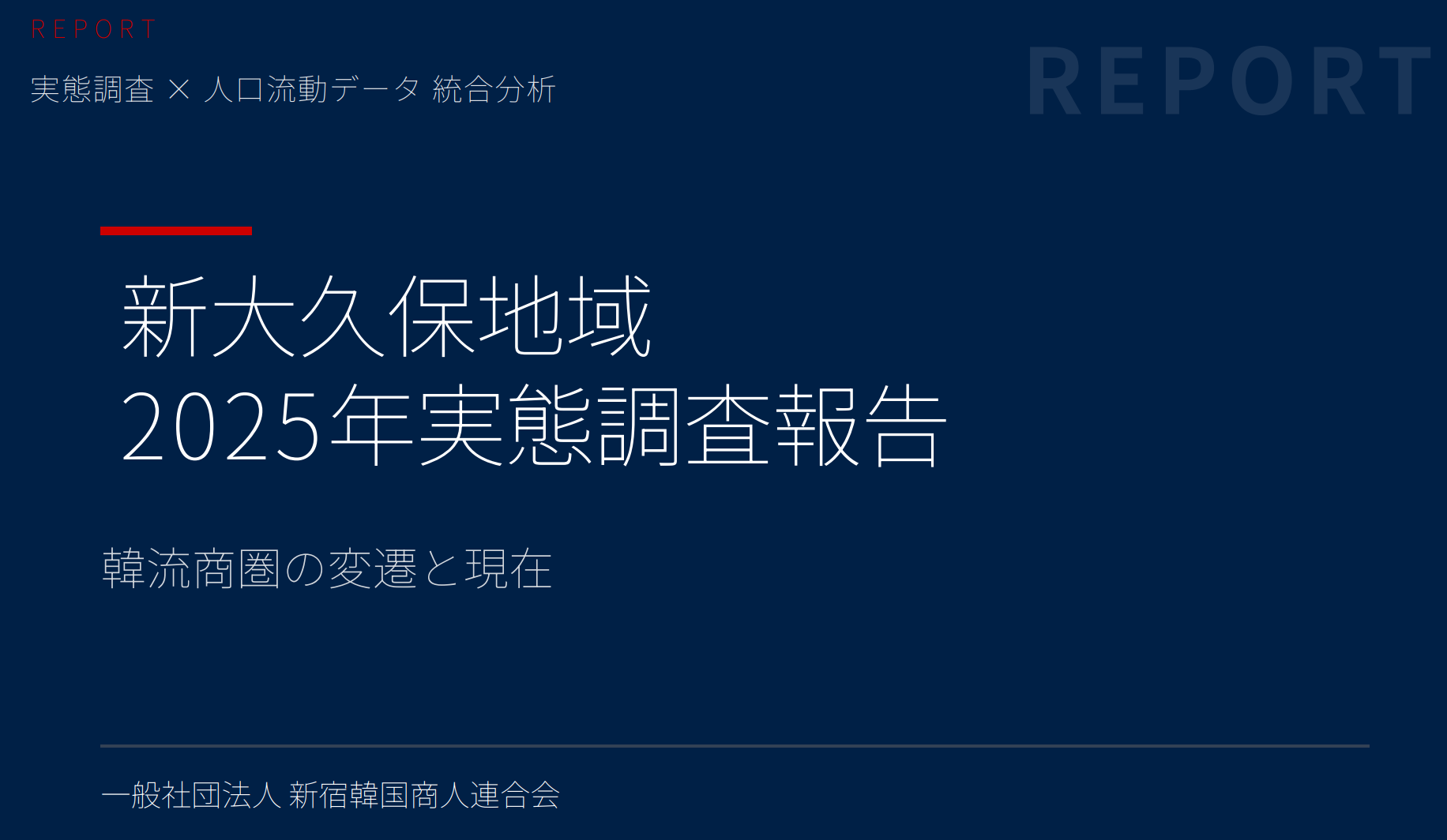





Leave a Reply