‐早稲田大学朴相俊教授が見た日本企業の生き残り方
‐組織内で危機意識共有・ライバル企業との提携など
‐デスバレーの経験により既存の経営方針から脱皮
「毎瞬間、改革しなければならない」
失われた20年という「死の谷間(デスバレー)」を乗り越えた日本企業の最近の経営トレンドは「常時改革」だ。
日本の不況克服期を「不況トンネル(2016年)」と「不況脱出(2019年)」の2部作で発表した早稲田大学の朴相俊(パク・サンジュン)教授は「最近の日本企業は”黒字構造調整”だったり、”毎瞬間、改革しなければならない”という言葉をひときわ強調しているが、これは過去の日本型経営には無かった現象」だと話した。
朴教授は25日、東京の早稲田大学近くにあるホテルで行なわれた本紙とのインタビューで、日本企業が改革の常時化を強く主張する理由について、一言で「失われた10年、20年の代償が非常に大きかったため」だと答えた。
全般的に日本社会は変化よりも持続と安定、順応に対する慣性が強い。ものづくり企業が多い事もこの様な特性の現れだ。それ故に外部からの突発的な危機に脆弱な面も無くはない。
朴教授は「バブル崩壊当時、相当数の日本企業が”最後の瞬間”に至って初めて変化を選択し、それ故に犠牲と費用が非常に大きかった」と、「その時の経験を元に、選択と集中を通じ、常時構造調整を行なっている」と話した。現状黒字が出ていても、今後競争力が低下する事が判明すれば、果敢に整理するという意味だ。実際に日本企業は最近、人工知能(AI)、自動運転車、ドローン産業、6世代(6G)通信など、4次産業革命分野を中心にした事業構造の改編に拍車を掛けている。
「明」があれば「暗」もある。常時的黒字構造調整は終身雇用の基調が強い日本社会に、雇用不安という新たな課題を投げ掛けている。
朴教授は過去、1990年代、2000年代の暗黒期を脱出した日本企業には大きく3つの「秘密」があると話す。それは経営者のリーダーシップ、組織内の危機意識共有、生き残るためには「敵と手を握る」事も厭わない企業間提携の風潮だ。
日本の「100年企業」日立製作所がその代表例だ。朴教授は「日立は2009年に7873億円というとてつもない赤字を記録し、果たしてこの会社は生き残る事が出来るのかとの考えを抱く程だった」と、「新リーダーを中心に、競争力が無い事業は全て売却し、ソリューション事業に方向転換した事で、現在は完全に違う会社になった」と話した。一度方向を決めれば躊躇せず突き進むという話だ。
日立の復活を率いた川村隆前会長は、今でも日本のサラリーマンや大学生らにとって憧れの対象だ。川村前会長は過去、日立が劇的な変化が可能だった背景について「痛みが避けられない構造調整を進めながら、組織に活力を吹き込む成長戦略を同時に推進したため」だと、「構造調整だけをしたならば、片手で拍手をする様なものだった」と話している。ムチだけを振り回しても駄目だという言葉だ。
朴教授は「日本企業には従業員を解雇する事を負担に感じ、恥だと考える雰囲気がある」と、「困難な状況でも雇用を守るという事に対し、一種の自負心がある」とみている。また「この様な経営観により、賃金を削ってでも解雇は最小限にする事で、日本経済が暗黒期を経て来た」と話した。
朴教授は「評判の良い日本の企業家と従業員の関係を見ると、リーダーは従業員を”後輩”と捉え、従業員は内部昇進を経て最高の地位に上り詰めた彼らを”先輩”として見ているという事が、韓国と一見比較される部分」だと話している。
一例として2018年からソニーを率いている吉田憲一郎社長は本社役員時代「我々は過去の良き時代、ソニーの栄光と共にあった。次の時代に、より良いソニーを譲り渡そう」と口癖の様に話していたという。
朴教授は「これはソニーの改革スローガンになった」と話している。
企業間の活発な合従連衡も危機脱出過程で日本企業が体得した経営術だ。朴教授は「日立は主力だった火力発電機事業を三菱重工業と統合し、統合会社の主導権を三菱重工業に渡すという大胆な決断をした」と、「トヨタがパナソニック、NTT、ソフトバンクなどと様々な提携を模索している事も、危機から得た提携の学習効果」だと話している。
■朴相俊教授の学歴
△早稲田大学国際学術院正教授 △前・国際大学准教授 △米ウィスコンシン大学経済学博士 △ソウル大学経済学科学士・修士
翻訳:水野卓
Copyright ©The financialnewsjapan. All rights reserved.












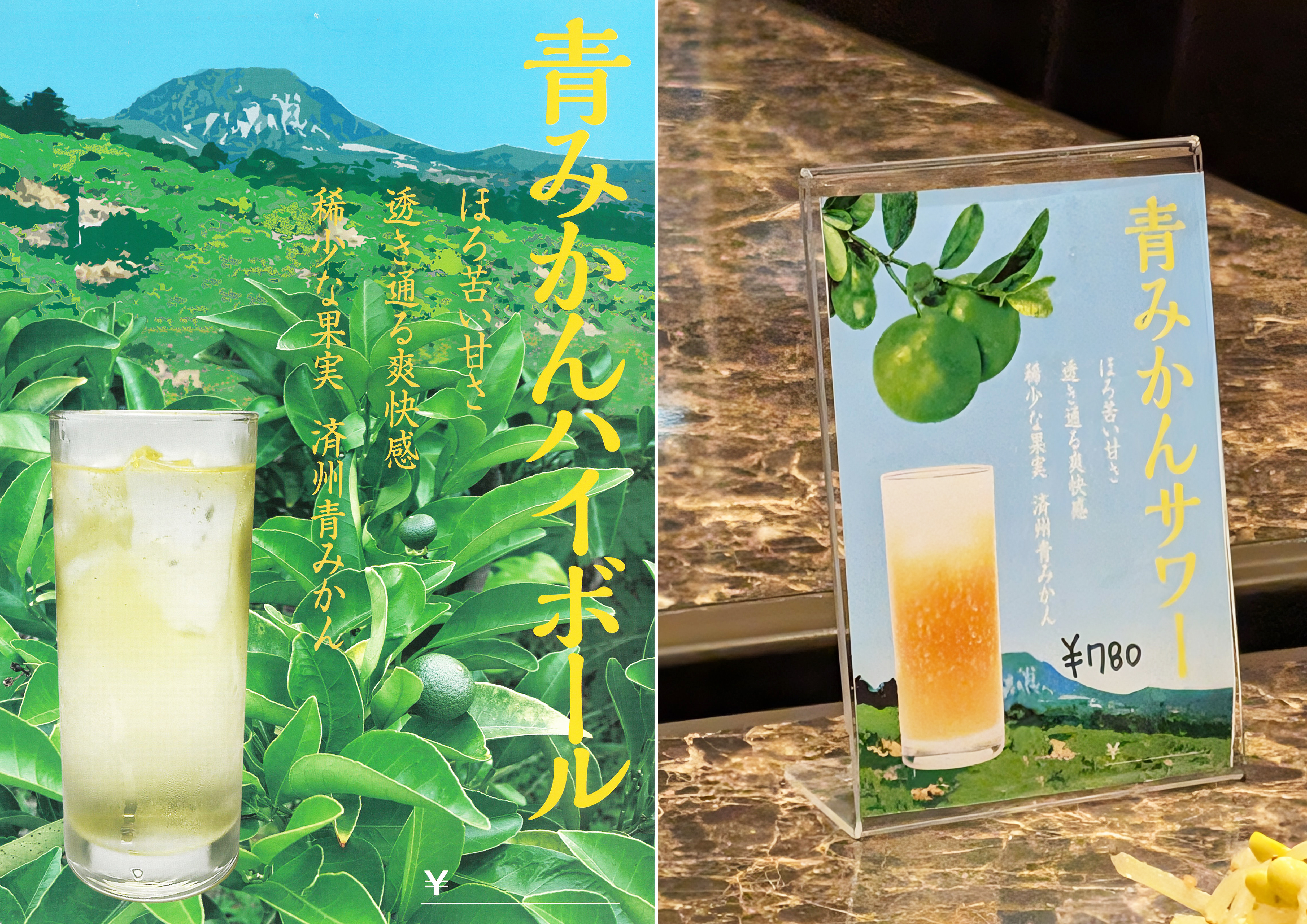
Leave a Reply