米朝首脳会談の舞台ベトナム、会談決裂にも「損してない」
米国と北朝鮮による2回目の米朝首脳会談が開催された2月28日、ベトナム・ハノイの グエン・ドク・チュン市人民委員会委員長(ハノイ市長)は異例にも市のホームページに公告を出した。同氏は「海外の記者や友人に、優雅で親切で教養のあるベトナム国民、ハノイ市民のイメージをアピールしよう」とし、首脳会談期間中に外国人対象のぼったくりをやめるように呼びかけた。
また、会談当日に約2万人の警察を市内のあちこちに配置して保安維持を徹底した。同処置が功を奏したのか、台湾EBCテレビの記者ピーター・ワンは米国メディアとのインタービューで、「去年1回目の首脳会談が開催されたシンガポールでは米朝首脳のスケジュール情報を割と容易く入手できたが、ここでは何の情報もない」とし「ここは非常に厳しい。警察が何ブロックの前から道路を封鎖している」と述べた。
今回の会談にかかった正確な費用については正確に公開されていないが、経費のほとんどはベトナム政府が負担したという。このようにベトバムが会談に力を入れた理由は明確だ。1975年ベトナム戦争の終戦以降、立ち遅れた共産国家から、先進国に負けない普通国家へ転じた威信を世界に知らしめるためとみられる。
1986年改革・開放政策である「ドイモイ」で資本主義の経済秩序を受け入れたベトナムは、国家主導の成長を追求してきた。経済開放の重要性を認識したベトナム政府は1990年代に入ってから宿敵だった米国との関係改善を進めた。その結果、米国政府は1994年にベトナムに対する経済封鎖を解除し、国交正常化にも合意した。
それから1年後、ベトナムは東南アジア諸国連合(ASEAN)に加盟し、2007年には世界貿易機関(WTO)に入った。去年ベトナムの経済成長率は6.7%を記録した。国民平均年齢は30.5歳で非常に若い。現在ベトナム政府は、2045年には先進国の仲間入りを果たすという目標を掲げ、経済開発を急いでいる。
ベトナムは物質的発展と同時に国際社会から認めてもらいたがっている。その一環としてベトナム政府は2020〜2021年の間、国連安全保障理事会の非常任理事国として入るという目標を掲げ取り組んできた。
2006年と2017年にはアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会談を誘致し、他にも小規模のアジア会議を組織し、ベトナムの位相を高めた。また去年6月には再生エネルギー発展規模を3倍にまで増やし、各家庭の太陽エネルギー使用量を2030年まで26%高めると宣言するなど、環境に優しい国家のイメージを強調してきた。
政府系シンクタンクのオーストラリア戦略指針研究所(ASPI)のレトゥルアン専任研究員は今回の会談を控え「仮に“ハノイ”という名を付けた平和協定や宣言が出るのなら、ベトナムとってはベストな結果になる」と評価した。
米朝首脳会談は決裂で終わったが、だからといってベトナムが今回の会談決裂で損した訳ではない。多国籍メディア分析業者のメルトウォーターによると、去年6月、1回目の米朝首脳会談の場所であるシンガポールが得た広報価値や広告利益などは約620億円だとされている。当時シンガポールが会談で支出した費用は約16億円だという。
他にも、トランプ米大統領は2月27日グエン・フー・チョンベトナム国家主席を会った席で、会談開催地の提供に感謝するとし、今年中にグエン主席を米国へ国賓として迎え入れると明らかにした。特にトランプ大統領は、ベトナムが米製の軍事装備品購入を検討しているところに感謝しつつ「これから私たちは友達」と強調した。
現在、南シナ海の領有権を巡り、中国との関係が悪化しているベトナムとしては米国との連携が切実な状況である。
今回の会談決裂でベトナムは目標としていた名声は獲得できなかったものの、少なくとも損はしていない模様だ。
翻訳:尹怡景







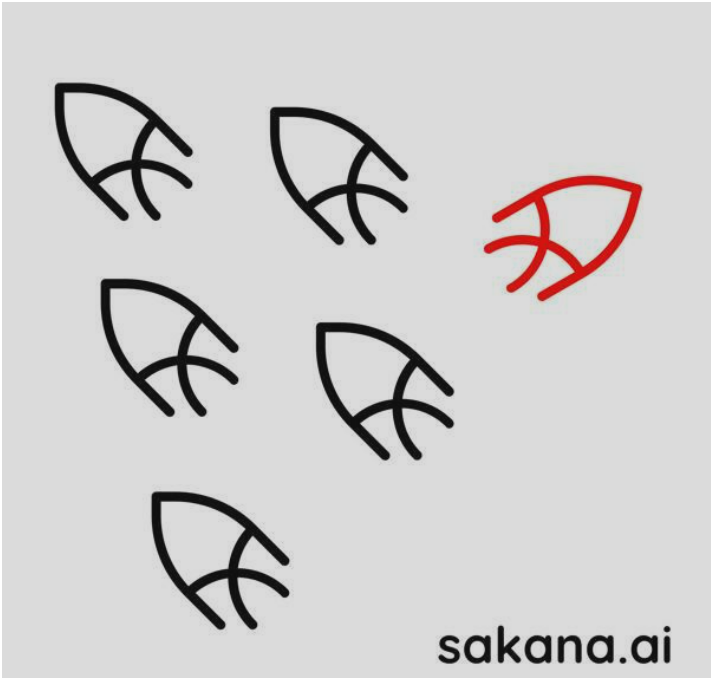





Leave a Reply