拡大するAI活用、日本の7原則と中国の限界
中国の指導部が人工知能(AI)をテーマにセミナーを開催した。このような国を挙げての産業政策に舌を巻く西欧諸国も多い。AIは今後、各国の産業競争力を牽引する核心分野であるためだ。
AIを巡っての論争は大きく二つに分かれる。一つは無限の活用範囲、もう一つは倫理問題だ。前者はAIの活性化を通し産業主導権を獲得したい各国の政策、そして後者はAIの過度な活用によって起こりうる倫理問題への懸念につながる。
最近は後者の問題に焦点を当てたAIの倫理ガイドライン作りに関心が集まっている。
日本政府が制定したAI活用の7原則では、まず最初に「AIは人間の基本的人権を侵害しない」という項目が記されている。その他には、厳重な個人情報管理やセキュリティ措置、そしてAI導入に対する企業の説明責任なども注目される。日本政府の「AIの7原則」は、AIは人間の人権を侵害してはならないということ、そして最終的な責任は必ず人間が負うという基本精神を盛り込んだ。
対する米国はグーグルやアップル、フェイスブック、アマゾンなどIT企業がAI開発を主導し、関連のガイドラインを設けている。欧州連合(EU)も米国と中国の「AI崛起」に対抗するため年末までにガイドラインを作成する方針だが、特に企業側の説明責任に重きを置いているという。
中国では現在BAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)と呼ばれる企業らがAI分野を主導しているが、実際には予め国家で政策の大枠を取り決めた上で、企業に課題を投げかける方式だ。結果的にAIの活性化と倫理問題は国家が管轄する事案となっている。
広範囲なデータが得られるという点から、AI分野では他国に比べ有利とも言える中国。しかし一方で足かせもある。社会主義を維持するための思想および情報統制が、AIの活性化に支障をきたす恐れがあるためだ。
中国では、AIチャットサイトが突如サービスを中断する事態が最近起こった。チャットAIが政治的な質問に対し、共産党そのものや中国の夢思想を否定するような内容の回答を相次いで出したためと見られる。同事態が代表的な例だが、中国のAI事業は光と影の側面を同時に抱えている模様だ。
翻訳者:M.I


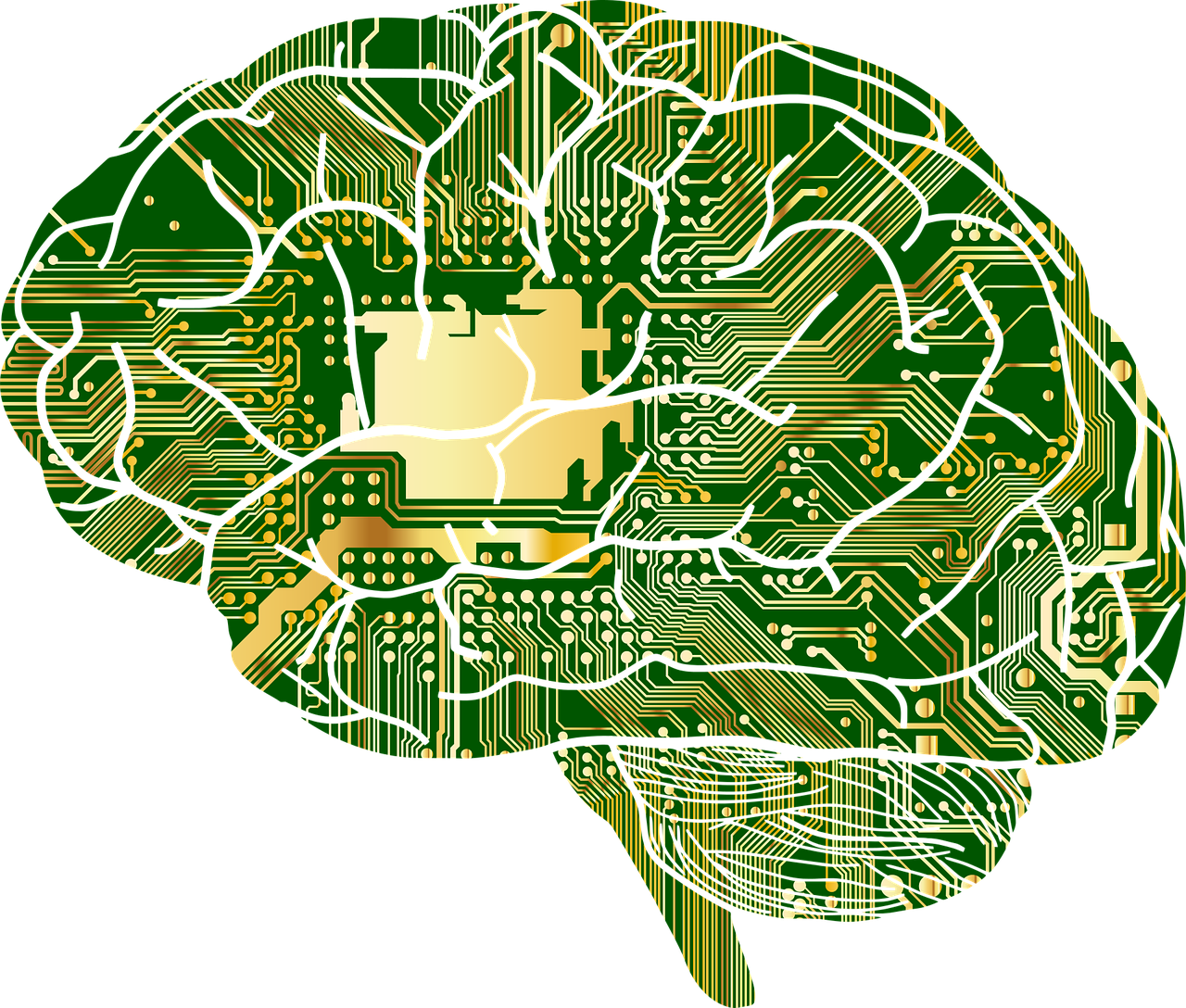




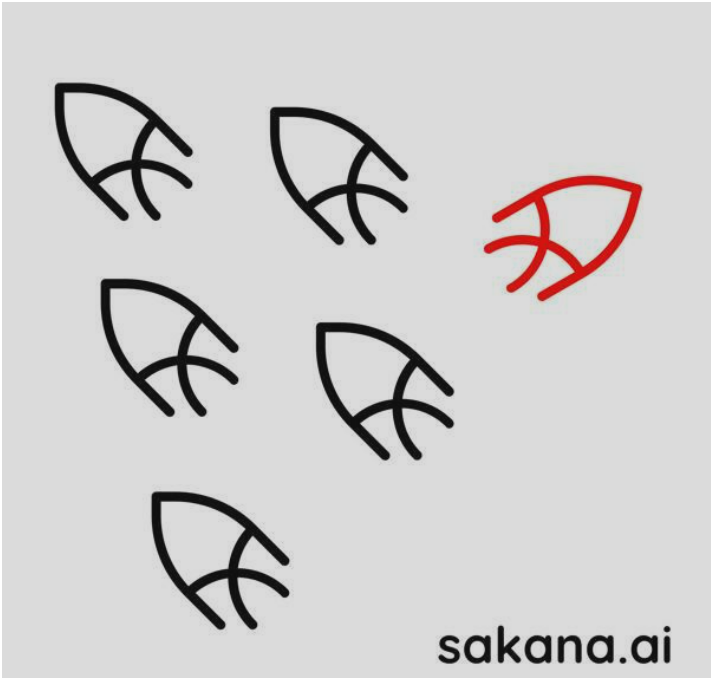





Leave a Reply